「part5の勉強を始めたいけど、何から始めれば良いか分からない…」
「part5に時間をかけすぎて、part7に時間を回せない…」
今回は、これからpart5の対策をする方、part5で時間を使ってしまって、part7に時間を回すことが出来ない方にオススメの1冊を紹介します。
こちらの本です。

こちらは関正生先生が書いた『関正生のTOEIC L&R®テスト文法問題神速100問』です。
これまで、関先生の参考書で勉強してきた人や映像授業を受けていた人は、手に取ってみてはいかがでしょうか。
この記事の後半では、姉妹本の「語彙問題神速100問」にも言及しています。
私は、800点前後の時に、『文法問題神速100問』で勉強していたのですが、この本で知識の抜け漏れを埋めることが出来て無事に930点を取得することが出来ました。

それでは、この本について色々紹介していきます。
感想
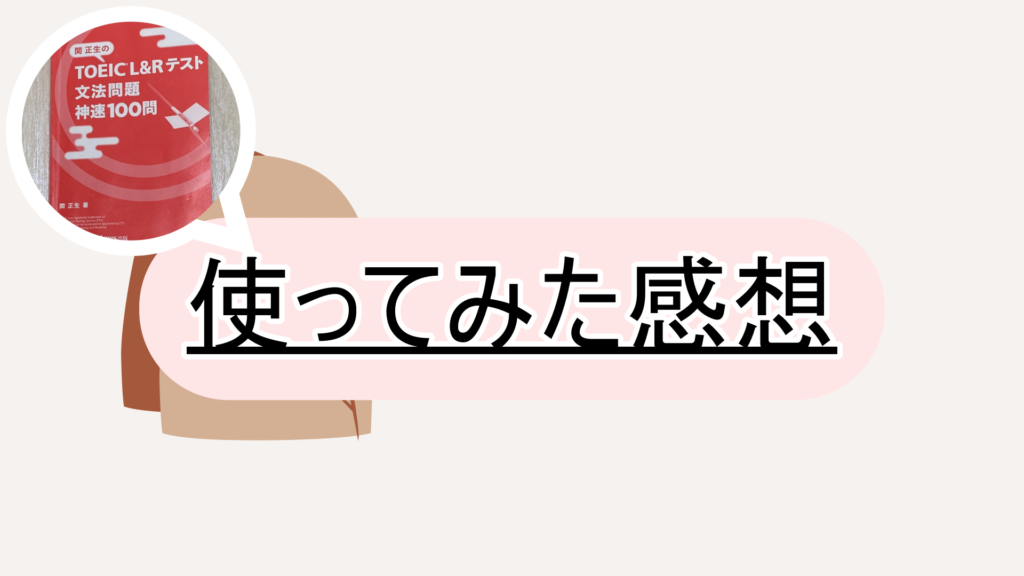
解説も分かりやすく、知りたい表現が整理されていて、知識の抜け漏れを埋めることが出来ました。
非常に良い1冊です。
私は800点前後の時にこの参考書で勉強しましたが、だれが使っても、有益な知識を知ることが出来るので、おすすめです。
特に、中級者(500~700点)の方に使っていただきたい1冊です。
オススメできる人
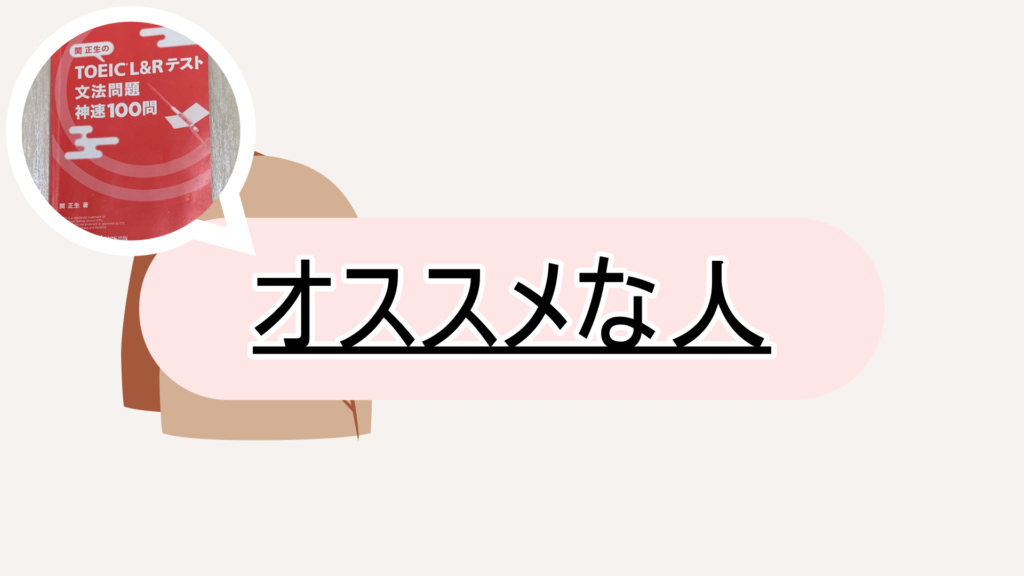
ほとんどの人にオススメできますが、特に以下に当てはまる人に最適だと思います。
- これからpart5の対策をする人
- 量よりも質を重視する人
- 知識の抜け漏れを埋めたい人
1つずつ説明していきます。
これからpart5の対策をする人
よく、「part5は解きまくれ」というアドバイスがありますが、それはpart5の基礎が付いている人がする勉強法です。
この参考書では、1問ずつかなり丁寧に解説されていて、問題数も多くありません。
なので、この参考書でしっかりと基礎をインプットするという点では、1冊目にちょうど良い参考書です。
基礎をインプットしてから、大量の演習問題でアウトプットすることをオススメします。
量よりも質を重視する人
この参考書は、1問を見開き1ページで解説しています。
また、1問につき2つのポイントがあり、1問に対しての密度がかなり濃いです。
1問ずつじっくり知識を吸収したい方には最適な1冊だと思います。
知識の抜け漏れを埋めたい人
私は、知識の抜け漏れを埋めることを目的にこの参考書を勉強しましたが、予想以上に新たな知識を吸収することが出来ました。
問題自体の難易度はそこまで難しくありませんが、解説が丁寧で、語法や多義語、様々な表現がまとめられているので、一気に抜け漏れを埋めることが出来ました。
相当英語上級者以外の人は、新たに得ることがあるでしょう。
良い点・悪い点
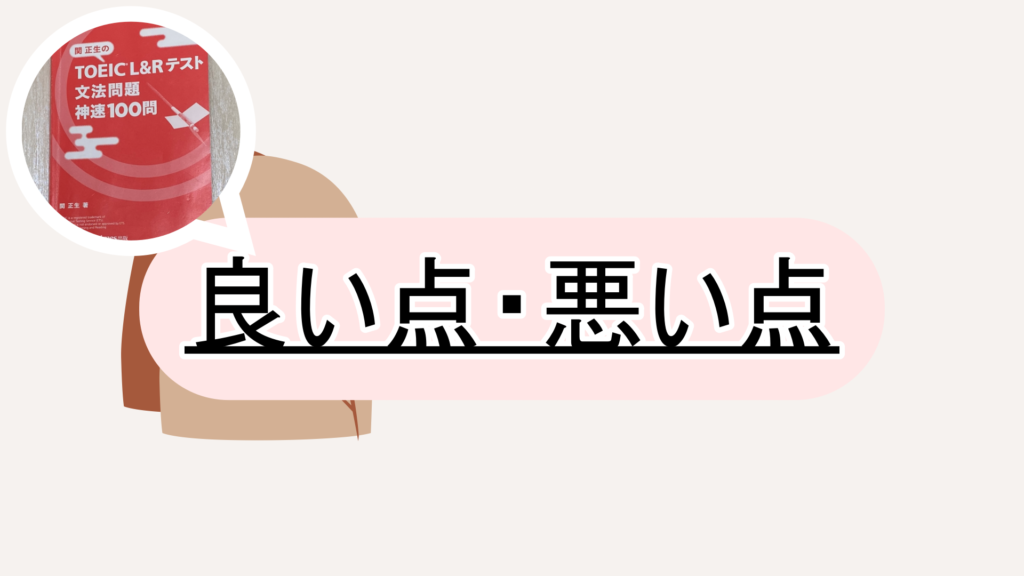
では、使ってみて分かった、この参考書の良い点と悪い点を紹介していきます。
先にまとめておきます。
- 良い点
- 様々な表現がまとめられている
- 考え方が身に付く
- 解説が分かりやすい
- 悪い点
- 演習量が足りない
- 音読用例文が欲しい
良い点から先に1つずつ説明していきます。
良い点
〈様々な表現がまとめられている〉
この本を学習する人の実力とタイミングによると思いますが、私が学習していて、最も「良いな」と思った点です。
様々な表現とは、例えば、「自動詞と紛らわしい他動詞」や「複合名詞」などのことです。
これらの表現や単語がまとめられている参考書は、これまでにあまり見たことが無く、出てくるたびに覚えるという勉強を繰り返していました。
なので、初めて、きちんと整理されている表を見た時は「目から鱗」でした。
他にもいろいろな単語の語法も載っていますので、語法が苦手という人にもおすすめです。
part5、6では語法を知っているだけで正解することが出来るラッキー問題もありますので、自信がない方は手に取ってみて下さい。
本番直前に、まとめられている表や語法を見るだけでも効果的です。
〈考え方が身に付く〉
解説ページに「ここで解く!」というものがあり、英文のどこに注目することで、正解できるかというのが視覚的に分かるようになっています。
また、ほぼすべての問題の解説が「~がポイントです」から始まり、注目するべき単語や品詞を教えてくれます。
その解説が丁寧で、同じ解説が繰り返しされている時も何度かありました。そのおかげで自然と復習にもなり、考え方も身に付きます。
この本の紹介文にも「思考プロセスを言語化する」という文句があり、まさにその通りでした。
これまで、なんとなく感覚で解いていたという人は是非読んでみて下さい。
まずはしっかりと理論を理解してから、感覚で解けるようにしましょう。
〈解説が分かりやすい〉
この本を書いたのは「世界一分かりやすいシリーズ」で有名な関正生先生です。
この本も、例にもれず解説が丁寧で分かりやすいです。
先ほども言いましたが、1問につき見開き1ページでたっぷり解説しています。
また、英語が出来る人の脳内を言語化しているので、正解までのプロセスを理解することが出来ます。
まずは、この参考書で正解の道筋を学んでから、演習問題で定着させることをオススメします。
以上3点が良い点になります。
悪い点
悪い点を紹介していきますが、あくまで私の感想で、人によると思います。
〈演習量が足りない〉
この本は全部で102問しかないので、思考プロセスを理解できるとは言っても、慣れるためにもたくさんの問題に触れる必要があります。
なので、演習用にこの本を買うことはオススメしませんが、冒頭でもお伝えしたように、1冊目の本には最適だと思います。
演習用にオススメな参考書として、TEX加藤先生が書いた「文法問題でる1000問」
または、同じ関先生が書いた「極めろ!リーディングpart5&6」が挙げられます。
私が使用していた参考書は、関先生の参考書です。
もし、「文法問題神速100問」を学習してみて、分かりやすいと思ったら、「極めろシリーズ」をオススメします。
関先生が書いているので、解説がつながります。
「極めろ!リーディングpart5&6」については以下の記事で詳しく解説しています。
〈音読用例文が欲しい〉
『文法問題神速100問』のすべての問題文は「abceed」というアプリで音声を聞くことが出来ます。
なので、音読学習もすることが出来ますが、音読をする際に答えが空所になっているので、少しだけ音読がしにくいなと感じました。
part5対策の本で、『金の文法』『TOEIC900点特急part5&6』には音読用例文が付いています。
音読用例文の使い勝手が良かったので、同じように、この本にも音読用例文が欲しいと思いました。
ただ、音読は別の教材でしているという人は特に何のデメリットにもなりません。
以上2点が悪い点でした。
もう1度良い点・悪い点を確認しておきます。
- 良い点
- 様々な表現がまとめられている
- 考え方が身に付く
- 解説が分かりやすい
- 悪い点
- 演習量が足りない
- 音読用例文が欲しい
使い方

この参考書は模試ではなく対策本なので、問題文は最初から最後まで読むようにして下さい。
選択肢を先に見たり、空所回りだけを見て解くのはやめましょう。
それ以外は特別な使い方はなく、普通に進めていくだけです。
進め方は以下の3つです。
- 1問ずつ進める
- 6問ずつ進める
- 30問ずつ進める
『文法問題神速100問』は、見開き1ページに6問の問題が載っており、6問ずつ解けるようになっています。
ただ、解説ページでも解けるようになっているので、1問解いて、その場で解説を見ることも出来ます。
また、この本は次のように3チャプターに分かれています。
- チャプター1 30問
- チャプター2 30問
- チャプター3 30問
- チャプター4 12問
以上のようになっているので、30問一気に解くことも出来ます。
どんな進め方でも良いと思いますが、この本が1冊目の人は、前半2チャプターを1問ずつ解いて、後半2チャプターを一気に解くという進め方でも良いと思います。
とにかく解説を読み込んで、理解することが大切です。
表に整理されている表現や単語はもちろん覚えた方が良いですが、何周もするので、1周目はそこまでムキになって覚える必要はありません。
次に、音読についてですが、私は解説を読み終わった後にその問題文を5〜10回ほど音読していました。
短文なので時間はかかりませんし、解説で理解したことを意識しながら音読をする事で、効果は何倍にもなります。
発音が分からなければ「abceed」で、簡単に聞くことができます。
5周するだけでも、各文を30回ほど音読したことになります。
以上で勉強法の紹介を終わります。
しつこいようですが、まずは解説を理解しましょう。
『語彙問題神速100問』との違い
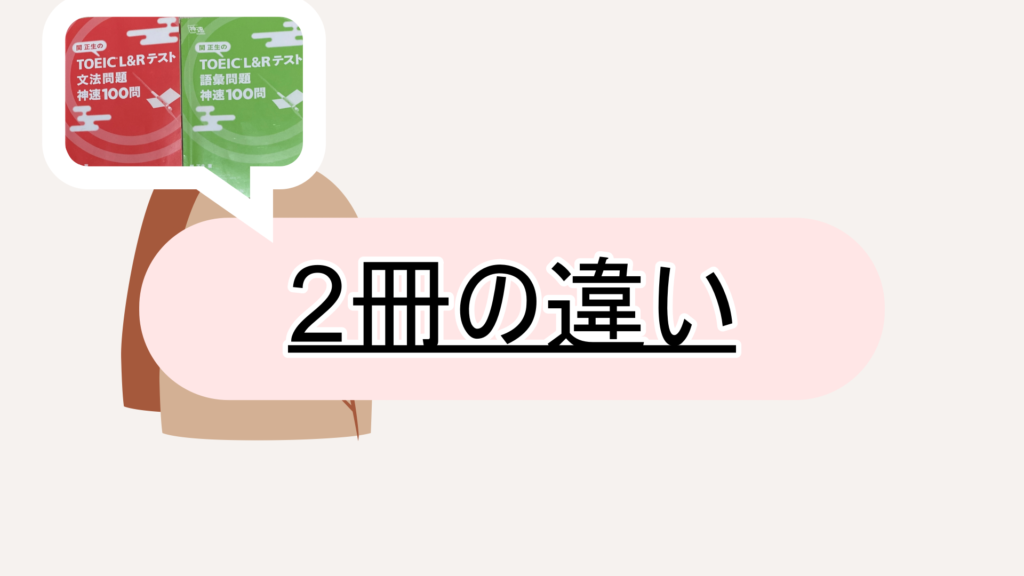
実は、これまで紹介してきた、『文法問題神速100問』の姉妹本?として、『語彙問題神速100問』という本があります。

左が今まで説明してきた本です。
この2冊の違いについて少し説明します。
part5には大きく分けて、以下の3つの出題パターンに分けることが出来ます。
- 文法問題
- 品詞問題
- 語彙問題
『文法問題神速100問』(赤い表紙)は、文法問題と品詞問題を中心に解説しているのに対して、
『語彙問題神速100問』(緑の表紙)は語彙問題を中心に解説しています。
それ以外はほぼ同じ構成です。
なので、これまでに説明してきた「おすすめできる人」「良い点・悪い点」「勉強法」も同じです。
ただ、『語彙問題神速100問』は、語彙中心の解説なので、『文法問題神速100問』ほど、「考え方」いわゆる「思考プロセス」が説明されていない部分もあります。
なので、まずは『文法問題神速100問』から学習をしましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
これからpart5の勉強をしたい人は、是非この本で基礎固めを徹底して下さい。
そのあとは大量の演習問題で知識を定着させましょう。
part5に手を焼いている人は、ぜひ、手に取ってみてはいかがでしょうか。
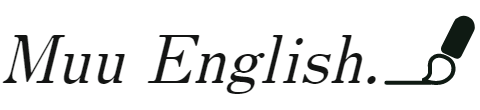


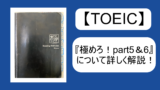


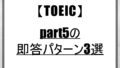

コメント